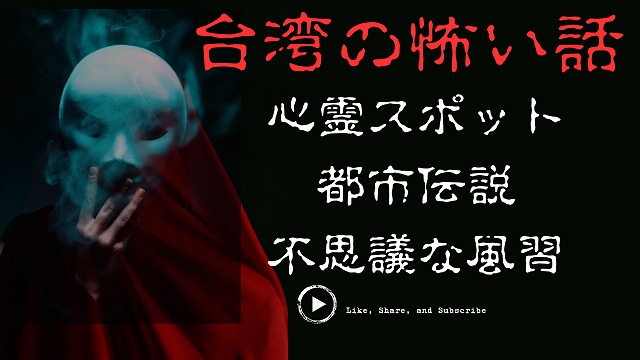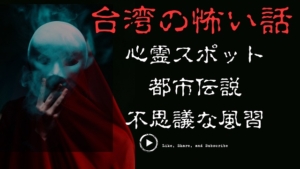台湾──その土地は、美しい自然と歴史が織りなす風景の奥に、
静かに息づくもうひとつの顔を持っています。
近年、その影を映すかのように台湾ホラー映画が注目を集め、
日本のホラーと同じ湿度を帯びた空気感が、観る者の心にじわりと忍び寄ります。
だが、台湾の不思議は映像の中だけにとどまらず、
日常の風習や語り継がれる都市伝説、
そして現地で訪れた心霊スポットの物語としても存在します。
日本と似ているようで異なる文化の狭間で、
そこに息づく禁忌や秘密を紐解くことは、
台湾をより深く知る旅の一端となるでしょう。
この記事では、そんな台湾の怖くも魅力的な話まとめ、
台湾好きな旅人の視点からお届けします。
紹介するスポットには立ち入り禁止の場所もあります。この記事は訪問を推奨するものではございませんのでご注意願います。
※今回の記事に繋がる台湾の宗教についてはこちらの記事もご参照ください。
読み進める前に知りたい鬼月とは
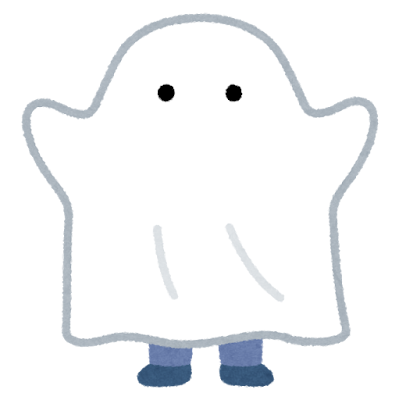
台湾では、旧暦の7月(農暦七月)を「鬼月(グィユエ)」と呼びます。
この月は地獄の門が開き、亡者や霊魂たちが現世に戻ってくると信じられており、日本のお盆に似た側面もありますが、より多くの禁忌(してはいけないこと)が存在します。
たとえば、鬼月の間は…
- 夜遅くまで出歩かない
- 海や川に近づかない(“水鬼”に引きずられると言われる)
- 壁に向かって口笛を吹かない
- 髪を乾かさずに寝ない
- 名前を大声で呼ばない
- 夜に洗濯物を干さない
- 結婚・引越し・開店などのお祝いごとは避ける
など、日常の中にも“霊に目をつけられないため”のルールが多くあります。
台湾の人々にとって「鬼」は恐怖の対象でありつつ、どこか身近な存在でもあります。
この鬼月の風習を知ることで、台湾の心霊スポットや都市伝説、ホラー映画に込められた背景がよりリアルに感じられるはずです。
具体的に鬼月っていつ?
旧暦(農暦)の7月は、西暦では毎年時期が異なりますが、だいたい7月下旬〜9月上旬のどこかになります。
例えば:
| 年度 | 旧暦7月1日(鬼門開) | 旧暦7月15日(中元節) | 旧暦7月30日(鬼門閉) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 8月16日 | 8月30日 | 9月14日 |
| 2024年 | 8月3日 | 8月18日 | 9月2日 |
| 2025年 | 8月23日 | 9月6日 | 9月21日 |
つまり、2025年の鬼月は8月23日〜9月21日ごろです。
この期間中、台湾各地では「中元節(地獄の門が最も開かれるとされる日)」に向けて「普渡」と呼ばれる供養儀式や祭りが行われ、町のあちこちにお供え物や紙のお金(紙銭)が並びます。
そんな鬼月には、怖いものをあえて楽しむ文化も根づいており(もちろん中には避ける方もいらっしゃいます)、ホラー映画が次々と公開されたり、テレビやネットでも怪談や心霊スポットの特集が組まれたりと、“霊的なもの”に対する注目が一気に高まります。
それではここから、実際に台湾各地に存在する心霊スポットや、それにまつわる都市伝説、不思議な風習、さらにはそれらをモチーフにした映画などをご紹介していきます。
心霊スポット
まず台湾各地の有名心霊スポットをご紹介していきましょう。
単なる怪談話にとどまらず、歴史・文化・映画とも密接に関わる場所ばかりです。
錦新大樓
台北の繁華街近くに位置しながら、数々の不幸な事件で知られる「錦新大樓」は、39年間で30件もの命が失われたとされる台湾でも有数の凶宅です。元は「時代大飯店」という住商混合のビルで、1984年には電線の火災によって19人が命を落とし、49人が負傷する大惨事が起きました。
その後も1986年の「燒肉粽事件」(女性が男女関係のもつれから身を投げた際、偶然下でちまきを販売していた男性に直撃した悲劇)や1996年の火災、2010年のカップルの死亡事件、そして2020年の飛び降りなど、数々の悲劇がこのビルを襲いました。こうした不吉な出来事から、一度「錦新大樓」に名称変更されましたが、凶宅のイメージは拭いきれません。
現地の訪問者や住民からは、エレベーターが謎の動きをしたり、冷気を感じたり、幽霊の目撃談も多数寄せられています。特に、配達員が体験した「エレベーターが急降下して封鎖された空間が現れた」という話は有名です。
錦新大樓の6階には、火災で亡くなった方々の霊を慰めるための「各姓氏聯合宗祠」が設置され、頂上階には土地公廟が鎮座。住民の心の拠り所となっています。一方で「怖いけど安い」という理由で多くの人がここに住み、部屋は頻繁に取引されています。
そんな錦新大樓の不気味な雰囲気は、台湾の人気ホラー映画『鬼天廈』にも影響を与えています。
映画では、都市部の老朽ビルを舞台に、現代人が霊的存在に巻き込まれていく恐怖が描かれ、現実とフィクションが交錯するリアリティが大きな話題を呼びました。錦新大樓のような“生と死が混ざり合う建築”の存在が、作品全体に深い恐怖の影を落としています。
錦新大樓は単なる心霊スポットではなく、歴史の悲劇と現代の人々の暮らしが交差する複雑な場所。台湾の怪談や心霊文化を知る上で欠かせないスポットです。
西寧國宅

若者文化とトレンドの中心地、西門町。ファッションビルやカフェが立ち並び、夜には屋台が並ぶこの街に、台北で最も有名な心霊スポットのひとつ「西寧國宅」が静かに佇んでいます。
この市営住宅は、もともとは普通の集合住宅でしたが、今では“猛鬼大樓”という不名誉な呼び名で語られることもあります。その始まりは、20年ほど前に起きた老婦人のエレベーター内での死亡事件。この出来事を皮切りに、不慮の事故や自ら命を絶つ人、原因不明の体調不良や怪奇現象が相次ぎ、これまでに30人以上が亡くなったとも言われています。
内部は老朽化が進み、異様に長くて薄暗い廊下が特徴。昼間でも光が届かない区画もあり、心霊体験を語る人も後を絶ちません。そのため、ここは台湾のホラー映画のロケ地としても頻繁に使われる場所となり、リアルな「恐怖の舞台」としてホラーファンにも知られています。
賑やかな街・西門町にありながら、そこだけ時が止まったような異様な空気をまとう西寧國宅。明るく開かれた都会の裏側に潜む、近くて遠い“もうひとつの世界”が、ここには確かに存在しています。
獅子林大樓

台北・西門町の中心にそびえる金色のビル「獅子林商業大樓」は、この街を象徴するランドマークのひとつです。
ゲームセンター、映画館、婚礼用品店、香港式の飲茶レストランなどが入居し、かつては“青春のビル”とも呼ばれる存在でした。
しかし、この華やかなビルには、あまり知られていないもうひとつの歴史があります。
実はこの場所、かつては日治時代の「東本願寺」があった跡地。その後、戦後の混乱期には中華民国政府の手に渡り、台湾省警備総司令部保安処が設置されました。1947年の二二八事件、そして1950年代の白色恐怖の時代には、ここで多くの政治犯が拷問や処刑を受けたともいわれています。
つまり、現在の獅子林ビルは「処刑場の跡地」に建てられた建物なのです。
こうした背景から、
- 夜中に人気のないフロアで、誰かに見られているような気がした
- 誰も押していないのに、エレベーターが止まらないはずの階で開いた
といった心霊体験や都市伝説が、SNSや掲示板などで今も語られ続けています。
このビルは1977年に着工し、1979年に開業。当時としては異例の20億台湾元もの巨額が投じられたことで注目を集め、低層は商業施設、高層は住宅やオフィスという「住商混合型」の先駆けでもありました。
しかし時が経つにつれ、出入口の複雑さや火災事故なども影を落とし、現在では「複雑な過去」と「現代の混沌」が交差する独特の空気をまとった場所となっています。
西門町という一等地にありながら、なぜか空きテナントが目立つ理由——
それは、もしかするとこのビルに染みついた、言葉にはできない“気配”と無関係ではないのかもしれません。
基隆鬼屋

基隆鬼屋として知られる林開郡洋樓は、台湾基隆市仁愛区にある1931年築の壮麗な西洋古典様式の邸宅です。三峡の炭鉱経営者であった林開郡が建て、その後賃貸住宅やバーなどに利用されました。特に戦後は「美琪酒吧」としてアメリカ軍人の憩いの場となり、1966年の米映画『砲艦サンパブロ』の撮影地としても使われています。
しかし所有権の複雑さや管理の難しさから長年放置され、建物は老朽化・荒廃した廃墟となりました。そのため「基隆鬼屋」と呼ばれ、台湾の心霊スポットとして全国的に有名です。地元では、かつてこのバーで働いていた女性がアメリカ兵との間に子を身ごもり、責任を取らなかった相手に怒って店に火をつけ、多くの人が命を落としたという悲劇の都市伝説が語り継がれています。以来、夜になると炎が見える、焼けただれた女性の霊が現れるなどの怪談が絶えません。
近年は基隆市文化局の支援のもと、所有者と協力して建物の修復が進行中で、2022年には期間限定で一般公開され、2023年には展覧空間が国際デザイン賞にノミネートされるなど、文化資産としての再評価も進んでいます。建物は、八角形の塔楼や空中庭園を備え、基隆港を一望できる優れた建築様式を誇りますが、周辺の高架道路建設により一部景観は変化しています。
基隆鬼屋は、歴史的価値と廃墟の怪談が交錯する台湾屈指のホラースポットとして、多くの観光客や心霊ファンを惹きつけています。
烏日鬼屋
台中市烏日区武光路にある4階建ての一軒家は、30年以上前にキャバレーで働く女性の資金援助によって建てられました。彼女は、事業に失敗して意気消沈した常連の実業家を助けるために再起資金を出しましたが、実業家が成功すると態度が変わり、彼女の入居を拒みました。深く傷ついた女性は赤いドレスを着て自宅で首を吊って命を絶ちました。実は実業家には妻子がいたのです。
その後、実業家の家族は奇病に襲われ、赤いドレスの女性の幽霊を目撃したことで恐怖に駆られ、引っ越してしまいました。この家では怪奇現象が多発し、特に旧暦の「鬼月」には地元で話題になります。
幽霊騒動が広がる中、地元の人々は誰も住まない土地のため資金を集めて購入し、建物を取り壊して恐怖を払拭しようとしましたが、女性の怨念を恐れ計画は実現しませんでした。
また、当時賭博好きだった村長は、幽霊屋敷なら誰にも見つからないだろうと考え、この家で友人たちとトランプをしていました。しかし警察に見つかり、慌てて逃げる途中で全員が足を骨折する事故が起きました。村長は「三晩泊まれば賭けに勝つ」と挑戦しましたが、初日の夜に幽霊に襲われて逃げ出しました。

民雄鬼屋
民雄鬼屋は、台湾嘉義県民雄郷にある廃墟となった屋敷で、台湾四大お化け屋敷のひとつとして有名です。1929年に建てられた3階建てのバロック様式の建物でしたが、現在は老朽化が進み、屋根がなくなり壁の一部が残るのみの状態となっており、ガジュマルの木に覆われた独特の雰囲気が漂っています。
この屋敷には幽霊が出るという噂が広まり、多くの怪談が語り継がれています。歴史的には、嘉南平原一の大富豪である劉家の邸宅であった一方、戦時中には日本軍の宿舎として使われ、その時期に起きた出来事が怪談の一因とも言われています。
こうした歴史と幽霊話が融合した民雄鬼屋は、台湾のホラースポットの代表格として多くの観光客や心霊ファンを惹きつけています。民雄鬼屋の隣には「鬼屋カフェ」もあり、訪れる人の興味を引き立てています。
また、この民雄鬼屋は心霊スポットとしての人気の高さから、映画化もされており、台湾国内外のホラーファンに広く知られています。映画では実際の廃墟の雰囲気や怪奇現象を題材にし、多くの観客に恐怖と興味を与えました。
↑実際に民雄鬼屋を訪れた際の動画はこちら
杏林医院
杏林医院は、台湾台南市にかつて存在した地域病院で、1975年に医師・黄森川氏らによって設立されました。開業当時は医療技術が評価され、市長からも信頼されていた名門病院でしたが、1991年に医療記録の偽造や保険金詐取、財務報告の不正などの問題が発覚し、1993年に閉院しました。
閉院後も建物は解体されず、当時の医療器具や薬品もそのまま残されていたため、次第にさまざまな怪奇現象の噂が広まり、地元で「台南の有名な心霊スポット」「台湾屈指の廃病院の幽霊屋敷」として知られるようになりました。テレビ番組などでも取り上げられ、都市伝説が多く語られています。
2018年に隣接する京城銀行に買収され、建物の一部は整備されて店舗として活用されていますが、心霊スポットとしての伝説は色あせていません。
2020年には台湾映画『杏林医院』が公開され、病院にまつわる怪奇現象を描いたストーリーで話題となりました。
Netflix会員の方はこちらから映画をご覧いただけます。
都市伝説
続いては台湾で有名な都市伝説をご紹介していきたいと思います。
台湾の風習や民間信仰に関連したものが多いのが特徴です。
紅衣小女孩(紅い服の少女)
台湾の都市伝説の中でも特に有名で謎めいているのが、「紅い服の少女」の話です。
1998年、台湾で人気を博した心霊番組に、1本の不気味な動画が一般視聴者から投稿されました。動画には、ハイキングを楽しむ普通の家族が映っていました。表面上はごく普通の様子でしたが、よく見ると家族とは異なる、真っ赤な服を着た少女の姿が静かに映り込んでいたのです。この投稿は大きな話題となり、「紅い服の少女」という都市伝説の火付け役となりました。
この少女は、台湾の妖怪「モシナ(魔神仔)」と結びつけられることも多く、モシナは赤いサルや子供のような姿をしており、時に人々を惑わしたり、警告を伝える存在とされています。単なる幽霊を超えた、台湾の民間信仰と深く繋がる不思議な存在なのです。
さらに、ある村で行方不明になったお婆さんが発見された際、彼女は「赤い服の少女と一緒にいた」と証言しています。少女は不安げに彼女を導き、山奥から安全に戻る手助けをしたと言われています。このエピソードは、紅い服の少女が恐怖だけでなく、哀しみや助けをもたらす二面性を持つことを示しています。
この都市伝説は、台湾で映画化もされており、その神秘的で恐ろしい物語は多くの人々の心に深く刻まれています。映像作品を通じて、紅い服の少女の伝説はさらに広がり、台湾の怖い話の代表格として今なお語り継がれているのです。
Amazonプライム会員の方ならこちらから映画をご覧いただけます。
赤い封筒
台湾の「赤い封筒(紅包)」にまつわる都市伝説は、未婚の女性が亡くなった際に遺族が赤い封筒を道端に置き、それを拾った男性が強制的に故人と冥婚(死者との結婚)を迫られるという怖い話です。しかし、この話は都市伝説であり、実際には非常に稀か、ほとんど存在しないと専門家は指摘しています。
実際の台湾文化では、赤い封筒はお祝いごとや感謝の気持ちを表すためのもので、日本のご祝儀袋のような役割を果たします。冥婚自体は伝統的な風習として存在しますが、より厳かで伝統的な儀式で行われ、故人の写真や遺品を用いて霊を慰め成仏を願うものです。
この都市伝説をモチーフにした台湾の人気アクションコメディ映画『僕と幽霊が家族になった件』は、主演に許光漢(シュウ・グァンハン)を迎え、幽霊との奇妙な共同生活をコミカルに描いています。台湾のみならず日本でも大変人気を博し、許光漢の魅力と演技力が映画の成功を後押ししています。
この映画は、伝統的な怖い話を現代風にアレンジし、幅広い世代から支持されているため、台湾文化や都市伝説に興味がある方はぜひチェックしてみてください。
Netflix会員の方はこちらから映画をご覧いただけます。
風習
最後は台湾の風習についてご紹介します。台湾には、日本とは少し違った独自の風習や信仰が数多く存在します。特に「鬼月(農暦7月)」や「信仰と結びついた日常のルール」など、地元の人々にとっては当たり前でも、旅行者にとっては驚きの連続。ここでは、そんな台湾ならではの不思議で魅力的な風習について、実体験を交えてご紹介します。
送肉粽(チマキ送り)
「送肉粽(粽送り)」は、台湾の民間信仰に根ざした特別な儀式で、首吊り自殺をした人の霊を鎮め、あの世へと送り出すために行われます。特に中部の彰化県鹿港などで伝承されており、故人の強い霊力が生者に災いをもたらさないよう祈願する、地域にとって非常に重要な風習です。
儀式は、道士によって厳粛に執り行われます。まず儀式の場所には結界が張られ、関係者以外の立ち入りは禁じられます。次に、故人が使った縄や触れた物品を清め、竹の棒に束ねた粽(ちまき)とともに、川や海の河口へ運び、焼却したり水に流すことで霊を弔います。
この粽には、肉やエビ、ピーナッツなどの具が詰められており、まさに“肉粽”を“送る”ことから「送肉粽」と呼ばれるようになりました。この一連の行為は、清めの意味を持ち、地域全体の安全や平穏を祈願する大切な儀礼です。
この伝統は、台湾ホラー映画『粽邪(The Rope Curse)/縄の呪い』シリーズでも取り上げられています。映画では、古くからの儀式とその背後にある霊的な力、そして現代社会との接点が描かれており、台湾の民間信仰とホラーが交錯する独自の世界観が話題を呼びました。
「送肉粽」は、単なる迷信やホラーではなく、死者への敬意や、残された人々の心のケアを目的とした重要な儀式です。台湾を訪れる際、このような風習の存在を知ることで、観光だけでは見えない深い文化や価値観に触れることができるでしょう。
Netflix会員の方はこちらから縄の呪い2をご覧いただけます。(1は探したけど見つかりませんでした。)
貼紅紙

最後に、私が台湾留学中に実際に体験した、現地の風習についてご紹介します。
ある夜、自宅の玄関に赤い紙が貼られているのに気がつきました。よく見ると、近所の家々にも同じような赤い紙が貼られていて、気になって調べてみたところ、それは「貼紅紙(Tiē hóngzhǐ)」という風習だとわかりました。
これは、近隣で誰かが亡くなった際に、遺族が周囲の家々に貼るもので、主に以下のような意味があるそうです:
- 魔除けや不運を遠ざけるため
- 弔問に訪れる親族が間違えて別の家に行かないようにするため
- 赤い紙を貼っていない家が遺族の家であり、故人が迷わず帰ってこられるようにするため
思いがけず台湾の文化を知ることができて貴重な体験でした。ただ、最近はこの風習を知らない若い世代も増えていて、間違って紙を剥がしてしまうこともあるそうです。
こういった風習に出会えるのは、旅行ではなかなかできない、留学ならではの特別な体験だなと感じました。
怖い話を通して見えてくる、もう一つの台湾
台湾は美しい自然や美味しい食べ物、温かい人々にあふれた国ですが、
その裏側には、長い歴史と信仰に根ざした数々の「怖い話」や「不思議な風習」が存在しています。
今回ご紹介した心霊スポットや都市伝説は、単なる怪談にとどまらず、
台湾という土地が大切にしてきた文化や価値観を映し出す鏡でもあります。
観光では見えにくい「もう一つの台湾」を知ることで、あなたの旅がより深く、印象的なものになるかもしれません。
信じるか信じないかは、あなた次第——
でも、夜道を歩くときは、くれぐれもお気をつけて。
また私のSNS、YouTubeでは最新の台湾情報を随時更新しているので、是非フォロー、チャンネル登録をお願いいたします。
Chan Kei Profile
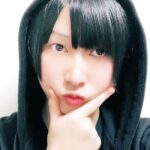
- 写真や動画を通して旅の魅力を伝えています。